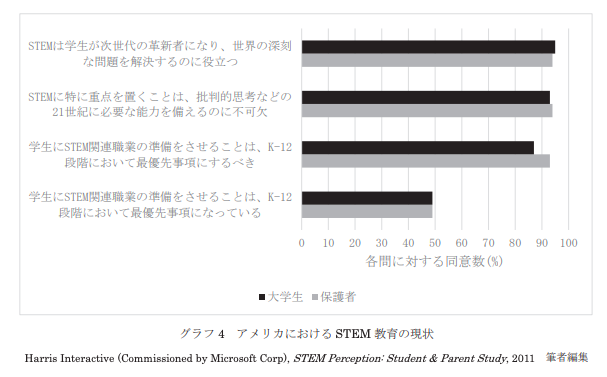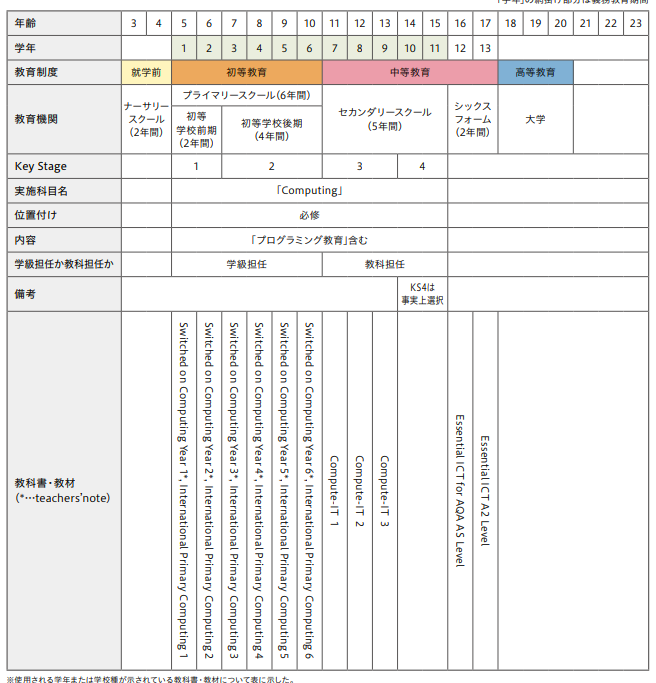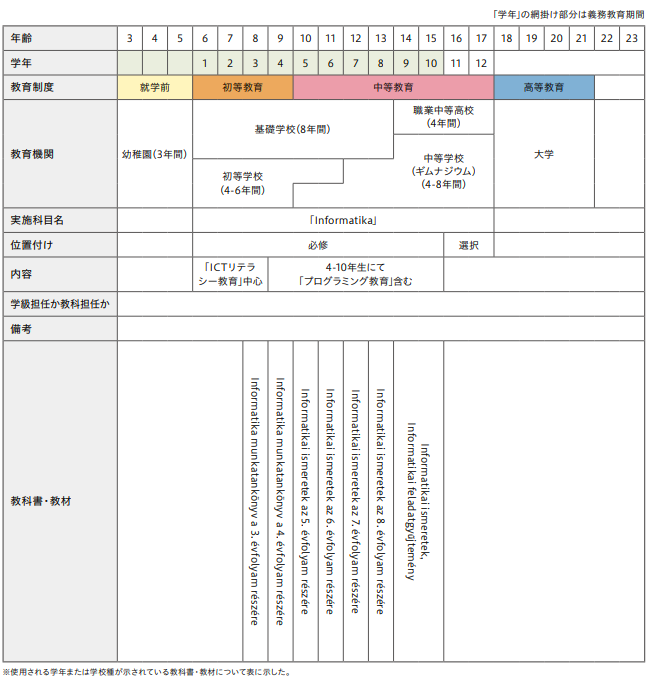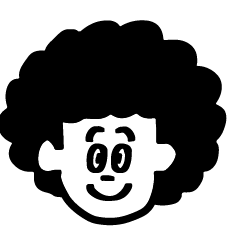IE-Schoolとして指定されている小学校6校のプログラミング教育事例を紹介しましたが、そこでは様々な成果と課題が浮き彫りになっていました。

ここでは、中学校・高校で指定されている8校で先行して行われているプログラミング教育の内容と、実施した後に見えてきた成果・課題についてご紹介します。
- 静岡英和女学院中学校・高等学校
- 古河市立三和東中学校
- 筑波大学附属駒場中学校
- つくば市立春日学園義務教育学校
- 神奈川県立住吉高等学校
- 早稲田大学高等学院
- 北海道浦河高等学校
- 宮城県多賀城高等学校
静岡英和女学院中学校・高等学校
プログラミング教育の内容
静岡英和女学院中学校・高等学校では、中学校2年生を対象に総合的な学習の「地域について考えよう」というテーマでプログラミング教育が導入されました。
地域について調べる際に、タブレットを使用して情報取集し、発表する際にプレゼンテーションアプリを使用しました。
プログラミング教育の成果
静岡英和女学院中学校・高等学校で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- 全教員が同じ方向を向いて情報活用能力の育成ができた点
- 情報モラルやセキュリティに関して、保護者からタブレットなどの使用に関するヒアリング・生徒からのSNS情報モラルに関するアンケートから年齢に応じた内容を明確化でき、年間計画に組み込んで実施することができた点
- タブレットなどのICT機器を利用することによる教員負担の軽減
- タブレットなどに不慣れな教員に対してICT支援員がフォローしたことで、ICT機器を利用した授業の展開ができた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
- ICTを活用してさらに情報活用能力を育成する方法論を展開していく点
- 情報モラルの年間計画に関しては、より専門的な見解を組入れるために静岡大学と連携していく点
古河市立三和東中学校
プログラミング教育の内容
古河市立三和東中学校では、中学校1年生を対象に数学の「量の変化と比例、反比例」の時間を使ってプログラミング教育が導入されました。
具体的には、(1)アプリを使って図やグラフを作成する(2)作成した図やグラフをアプリを使って共有・比較する(3)お互いの表やグラフの相違点・共通点を見つけ考察する、といったプログラミング教育が実施されました。
プログラミング教育の成果
古河市立三和東中学校で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- カリキュラムと発達段階に合わせた情報活用能力を明確化し、年間指導計画に落とし込んで実践できた点
- 情報ネットワークやICT機器といったハード面に関して、企業の協力を得て整えることができた点
- アプリの導入によって、アダプティブな授業展開・協働的な授業展開が可能になった点
- 環境整備によって、生徒がPCやタブレットなどのICT機器に触れる時間が増え、情報活用能力の育成に大きく寄与している点
- 有識者やNPO法人といった外部要員がプログラミング教育の現場に入ったことによって、より専門的なプログラミング授業を行うことができた点
- タブレットなどのICT機器を利用することによる教員負担の軽減
- タブレットなどに不慣れな教員に対してICT支援員がフォローしたことで、ICT機器を利用した授業の展開ができた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
- 他の学校と連携して、義務教育期間である9年間を通してプログラミング教育の研究を展開していく点
- 生徒の発達段階に合わせた情報モラルの展開だけでなく、保護者に向けた情報発信もしていく点
- 小学校・中学校でそれぞれに育成すべき情報活用能力を見極めて授業に取り入れていく点
- 現在、ICT支援員に生徒と同じPC環境が整っておらず、ICT支援員がアプリの内容を熟知できていないため、ICT機器の基本的な操作スキルの支援のみに留まってしまっている点
筑波大学附属駒場中学校
プログラミング教育の内容
筑波大学附属駒場中学校では、元来、クラウド環境を利用した学習を行っており、蓄積された活動記録や成果物はポートフォリオに落とし込み、その後の学習にも行かせるような素地ができていました。
そんな中、IE-Schoolに指定された年度は、中学校3年生を対象に総合的な学習で行った「物理パラメータとアルゴリズムの改良に着目した着陸ゲームの開発」の時間を使ってプログラミング教育が導入されました。
具体的には、(1)ゲームのアルゴリズムと変数を理解する(2)プログラムの仕組み理解(3)ゲーム実行のための合理的な方法を知る(4)プログラミングを使用て技術的な問題解決する、といったプログラミング教育が実施されました。
プログラミング教育の成果
筑波大学附属駒場中学校で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- 次年度実施の単元開発、授業設計、教材開発(インタフェースの改良、ライントレースカーの改良、制御モジュールの改良)ができた点
- 数学科(代数)、技術・家庭科、情報科、総合的学習の時間、特別活動に絞り、資質・能力ベースの情報活用能力の整理ができた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
つくば市立春日学園義務教育学校
プログラミング教育の内容
つくば市立春日学園義務教育学校では、第8学年を対象に数学の「一次関数」の時間を使ってプログラミング教育が導入されました。
具体的には、比較検討の場面でタブレットを用いて学習支援システムを活用することで、個人の意見をそれまでよりもスピーディに見比べ、より良い解決方法について議論できるようなプログラミング教育が実施されました。
プログラミング教育の成果
つくば市立春日学園義務教育学校で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- 筑波大学協力の下、ラズベリーパイを活用した「つくば市の中学生向けのネットワーク接続、サーバー構築体験イベント」が開催できた点
- 電子黒板を活用したプレゼンテーションの手引きの作成ができた点
- 推進校内における学園内プレゼンテーションコンテスト開催し、市内小中学生約1万人の参加を募ることができた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
- 小中学校9年間を通して情報活用能力を含めた21世紀型スキルが体系的に身に付けられるような指導計画を策定する点
- 小中学校および特別支援教育におけるプログラミング教育をさらに推進し、教科の中でのプログラミング学習の位置づけを図る点
- 電子黒板を使ったプレゼンテーションコンテストを市外にも拡大し実施する
- 現在、ICT支援員に生徒と同じPC環境が整っておらず、ICT支援員がアプリの内容を熟知できていないため、ICT機器の基本的な操作スキルの支援のみに留まってしまっている点
神奈川県立住吉高等学校
プログラミング教育の内容
神奈川県立住吉高等学校では、高校2年生を対象に地理歴史科・世界史Aの「ヨーロッパ・アメリカの工業化と国民形成 」の時間を使ってプログラミング教育が導入されました。
具体的には、タブレットを使用して学習した内容をまとめ、他者と協働で課題を作り、電子黒板を使用して生徒と教師の双方向の授業スタイルをとったプログラミング教育が実施されました。
プログラミング教育の成果
神奈川県立住吉高等学校で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- 「LEGOマインドストーム」を導入し、「社会と情報」でプログラミング教育を実践できた点
- 外部連携機関と共同した情報セキュリティに関する授業を実践した点
- 外部有識者を講師とした、プログラミング的思考を含む情報活用能力の育成や、アクティブ・ラーニングの視点に基づく授業づくりなどの教員研修を実施ができた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
- 次年度の年間指導計画の作成、教材の開発などに発展的に取組、情報活用能力の体系的な育成を図れぞれに育成すべき情報活用能力を見極めて授業に取り入れていく点
- 現在、ICT支援員に生徒と同じPC環境が整っておらず、ICT支援員がアプリの内容を熟知できていないため、ICT機器の基本的な操作スキルの支援のみに留まってしまっている点
早稲田大学高等学院
プログラミング教育の内容
早稲田大学高等学院では、高校1年生を対象に社会と情報の時間で「情報社会の光と影」という単元でプログラミング教育が導入されました。
具体的には、ウェブサイトに掲載されている多種多様な情報から適切に主査選択する、コンピュータを使用して発表に使用するスライドの作成といったプログラミング教育が実施されました。
プログラミング教育の成果
早稲田大学高等学院で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- 校内体制として、次年度のカリキュラム作成、教材の作成、他教科や課外活動との連携強化ができた点
- 環境整備として、電子テキストの導入・使用、無線LAN/クラウド型アプリケーションなどを整えることができた点
- 大学や企業から協力体制を整えることができた点
- 公開授業の実施や、情報関連学会への発表ができた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
- 全ての教科・教師がプログラミング教育が実践できていない点
- 現在は大学運営のネットワーク環境を利用しているので、今後は高等学校独自の環境配備をしていく点
北海道浦河高等学校
プログラミング教育の内容
北海道浦河高等学校 では、高校3年生の国語・現代文Bの時間を使ってプログラミング教育が導入されました。
具体的には、7グループに2台ずつタブレットを用意し、1台は情報蒐集用、1台は資料作成用に用いたプログラミング教育が実施されました。
プログラミング教育の成果
北海道浦河高等学校 で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- 指導モデルを開発できた点
- 遠隔授業システムによるプログラミングに関わる授業について、指導モデルを開発できた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
- 教科横断的な情報活用能力の育成について、各校の成果と課題等について検証する必要がある点
- 各教科の取組を俯瞰する全体計画を作成し、平成28年度に作成した年間指導計画を見直す手段としての有用性を検証する必要がある点
- 指導モデルの有用性を検証する必要がある点
宮城県多賀城高等学校
プログラミング教育の内容
宮城県多賀城高等学校では、高校1年生の災害科学・自然科学と災害A の時間を使ってプログラミング教育が導入されました。
具体的には、クローンについて賛成グループと反対グループに分け、タブレットを使って動画を確認したのち、賛成反対の意見をまとめて発表させ、情報が意思決定に与える影響について考察するというプログラミング教育が実施されました。
プログラミング教育の成果
宮城県多賀城高等学校で実施されたプログラミング授業の成果として、以下の点が報告されています。
- 他教科と学習内容を共有できた点
- 遠隔授業システムによるプログラミングに関わる授業について、指導モデルを開発できた点
プログラミング教育の課題
一方で、プログラミング教育の課題として挙げているのは、以下の点でした。
- 各教科・科目における学習目標の定着に寄与する効果を具体的に評価する手法が未だ確立できていない点
- 教材提示ソフトや動画、シミュレーションを用いた授業を行っていが、その使用が学習効果に及ぼす影響を示す指標が確立できていない点
- タブレットの活用効果を具体的に評価する手法を探っていくこと